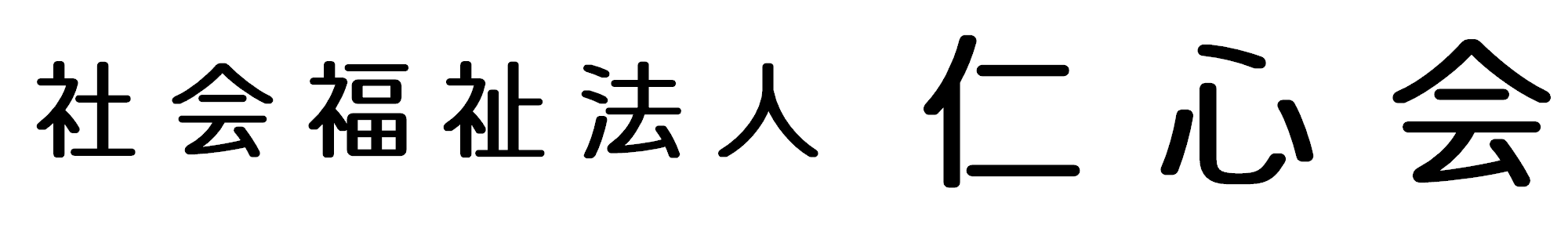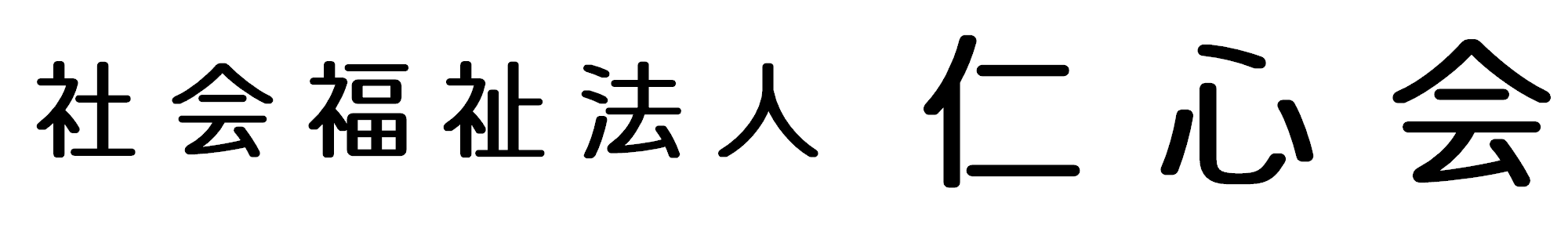|
 |
|
|
|
 |
■ 週休3日制度を導入! 夜勤を行う職員の身体の負担を軽減 |
仁心会では、2023年6月から、週休3日制度を導入しました。導入は段階的に行い、現在、「みと東部特別養護老人ホーム」の一部、「特別養護老人ホームかつた」で実施しています。週休3日制度を導入したことで、連休を取得しやすくなったりなど、夜勤を行う職員の身体の負担軽減につながりました。職員からも、「長い連休を取ることもでき、プライベートが充実する。」、「週休3日の場合、週休2日の場合と比べて1日の労働時間が長くなるが、仕事をしているとあっという間に時間が過ぎるので、1日の労働時間が長かったとしてもしっかり休める日があったほうがいい。」などと好評です。また、介護職の採用応募者数の増加にもつながりました。
さらに、計画的な有給休暇の取得促進も行っています。これにより、有給休暇の取得率は、75.3%(2024年1月~11月集計)となっており、日本の取得率の平均(2023年調査では62.1%)を上回っています。 |
|
|
 |
■ DX推進による情報共有 誰もが働きやすい職場環境に!残業時間も削減 |
仁心会では、PC、iPadを各フロアに配置し、利用者の見守り機器を導入したり、介護ソフトや給与、勤怠等のソフトを導入しクラウド化を行ったりなど、ICTの活用によりDXを推進しています。
DXを推進する最大の目的は、「情報の共有」です。これまでは、伝達事項を伝えるために、申し送りノートや、紙のメモや報告書を使用し、フォーマットもバラバラだったため、伝言ゲームのようになってしまい、情報が正しく伝わらないことがありました。そのため、グループウェアの導入や、報告書のフォーマットを統一することなどにより、情報の簡素化、視覚化、統一化を図りました。また、外国籍職員が業務をスムーズに行えるように、音声入力などの入力支援ソフトをタブレットに導入しました。これらの取り組みにより、“誰でも分かる”、“使いやすい”を実現することができ、外国籍職員や障害のある職員、短時間勤務の職員なども含め、全員が情報を共有することができ、業務の簡素化、効率化につなげることができました。このようなDX推進や、業務の一部を弁護士や社会保険労務士に外部委託するなどの取り組みにより、職員の負担軽減につながり、残業時間も少なくなりました。離職率は、取り組みを始める前(2019年8月)の7.5%から、2023年8月時点で1.6%まで低下しています。また、「茨城県働き方改革優良企業」の認定も取得しています。
仁心会では、ダイバーシティの推進とは、多様化すればするほど、業務をシンプルにしていくことだと考えています。外国籍の方、育児・介護を行っている方、障害のある方など、多様化する人材が働きやすい職場環境をつくることで、職員の「働きやすい改革」、「働きたい改革」の実現を目指しています。 |
|
 |

川村 康晴さん |
|
仁心会さんは、とても働きやすい環境であるように感じました。取材させていただいた中で、一番印象に残ったのは外国人技能実習生の方にお話を聞かせていただいた時のことです。流ちょうな日本語で話されていたので、私は半年ぐらい働かれているのかもしれないと勝手に想像していましたが、実際は1週間程度と話されていて、とても驚きました。そういった方でもしっかりと職場の戦力になっているように感じ、さまざまな工夫がされているのだなと思いました。「週休3日制」と聞くと導入されたら嬉しいが、夢のような話であるように私は考えていました。しかし、ICT化やDX化などさまざまな観点から仕事を削減して、実現することが可能だということを感じました。そして、有給休暇や育児休暇を含め休みやすい環境を作ることは、難しいように思っていましたが、ここでは当たり前であるような雰囲気があり、魅力的に感じました。
大学1年生のうちから、ダイバーシティを推進している企業に取材し、取り組みを知れたおかげで、自分が今後就職するうえで、こだわりたい点が徐々に具体的になってきているように感じ、良い機会となりました。
|
|

北野 有梨佳さん |
|
取材を通して、仁心会さんがD&Iに積極的に取り組んでいることがよく分かりました。様々な視点に立って物事を考え、社員全員が働きやすい職場を常に追求されている姿勢が非常に印象的でした。後半は車椅子の操作や介護食の試食など、実務的な体験もさせていただきました。利用者様の視点で実際に体験することで、新たな気づきも多く、大変貴重な機会となりました。
また、職員の方も利用者の方も皆さんが笑顔で、職場全体の雰囲気が温かく、居心地が良かったです。D&Iをはじめとした様々な取り組みに対する前向きな姿勢が、全ての人にとっての快適な環境を作り上げているのだと感じました。お話の中で「物事には全て原因(理由・根拠)がある」という部分が特に印象に残っています。思考を自動化してしまうのではなく、物事を多角的に考える習慣を身に付けていきたいと思いました。
|
|