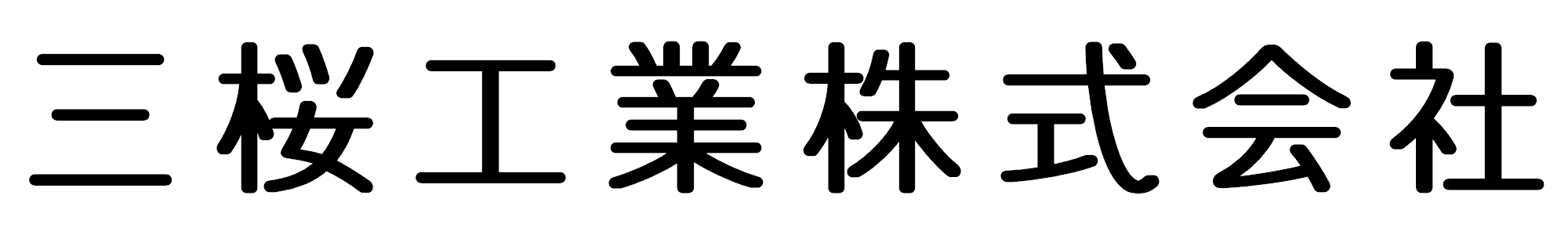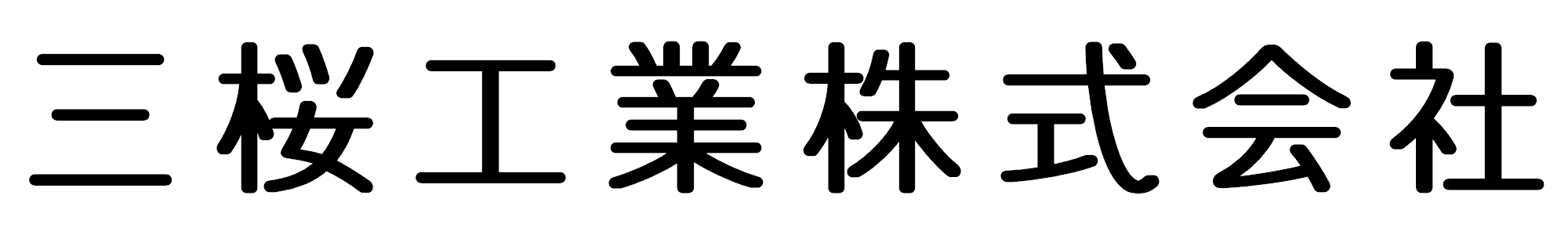|
 |
|
 |
|
 |
|
|
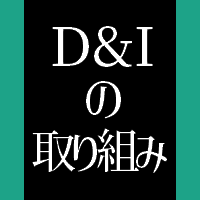 |
■外国籍社員が働きやすい職場環境づくり 表記の工夫やお祈り部屋の設置など |
三桜工業は、19か国に83拠点を有するグローバル企業であり、日本国内でも、20か国以上の外国籍社員が働いています。日本国内の事業所で働く外国籍社員の割合は約10%であり、コーポレート部門(人事、営業、研究職等)、製造部門問わず、さまざまな部署で活躍しています。そのため、社内の表示も日本語と英語の2パターンで作成したり、社員が集まる食堂など2か所にお祈り部屋(※)を設置したりするなど、外国籍社員が働きやすい職場環境づくりをしています。外国籍社員を対象とした座談会も実施しており、外国籍社員からは、多様な人材がいることや、グローバルな環境に対し満足の声があがっています。一方で、英語の社内使用率をもっと高めてほしい、といった声もあり、座談会を通して課題を共有し、さらなる環境の改善につなげています。
(※)お祈り部屋:イスラム教など、礼拝が義務付けられている宗教を信仰している方が礼拝できる場所。 |
|
|
|
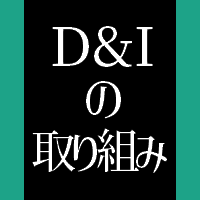 |
■社員の声を聞き、職場環境を改善 エンゲージメント調査、座談会、面談など |
三桜工業では、社員の声を聞き、職場環境の改善につなげる取り組みを多数行っています。
年に2回、育児座談会を実施しています。座談会では、育児経験者の話を聞いたり、会社の制度を知ったり、育児中の社員同士の交流を深めたりしています。また、アンケートなど文面だけでは見えてこない課題を吸い上げることができ、施策の検討にもつながっています。実際に、育児時短勤務について、子どもが小学校に入学する前までが対象だったものを、小学校3年生の末までを対象とするように変更しました。育児休業復帰支援面談も実施しており、育休からの復帰がスムーズに行えるよう支援しています。また、男性の育休の取得メリットを伝えるなどの取り組みにより、三桜工業の男性の育休取得率は、2023年度は60%を超えており、日本の取得率の平均(2023年度は30%)及び政府目標(2025年までに50%)を上回っています。
また、全員参加型の現場改善活動を行っています。職場での困りごとを、ネット上の専用フォームや郵便はがきで誰でも投稿できるようになっており、投稿された困りごとは、古河事業所の本部に届きます。困りごとは各事業部に展開され、改善計画を検討し、改善策を全社員で実行します。改善内容を全世界の事業所に共有し、会社全体の現場改善を行い、品質改善につなげています。(月次品質活動)
さらに、社員に対するエンゲージメント調査(※)では、その結果をもとにエンゲージメント向上プロジェクトチームと各部門が対話をし、最終的には各部門が自ら様々な施策を展開することで、組織全体のエンゲージメントを高めていくことを目指しています。
このように、社員の声を聞いて施策に反映させることで、社員が組織や仕事に主体的に取り組むことにつながります。社員全員が、職場環境改善への意識を持つことは、会社の風土が良くなることにもつながると考えています。
(※)エンゲージメント調査:従業員満足度とは異なり、従業員の所属組織に対する愛着心や仕事への情熱、従業員と組織の双方向の関係性や結びつきの度合いを指す。三桜工業では、ダイバーシティに関する設問も追加している。 |
|

|