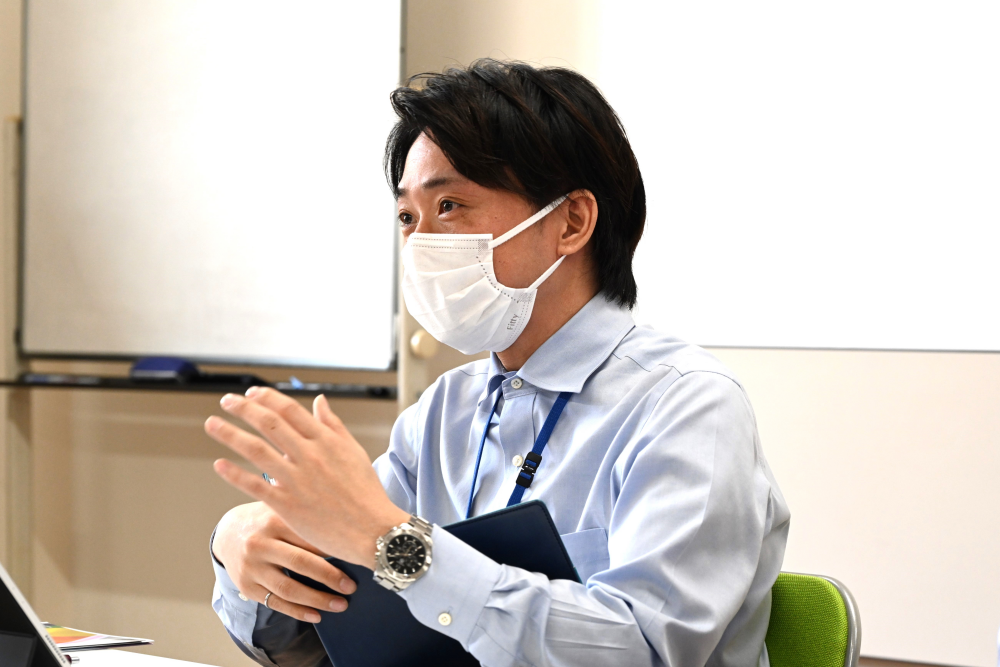ダイバーシティ経営の強みとは⁉ モデル企業のその後の取り組みについて伺いました。
2022年度紹介内容はこちら https://www.diversity-ibaraki.jp/score/taijinkai.html
2022年度紹介内容はこちら https://www.diversity-ibaraki.jp/score/taijinkai.html
 社会福祉法人 泰仁会 社会福祉法人 泰仁会 |
D&I推進モデル企業 |   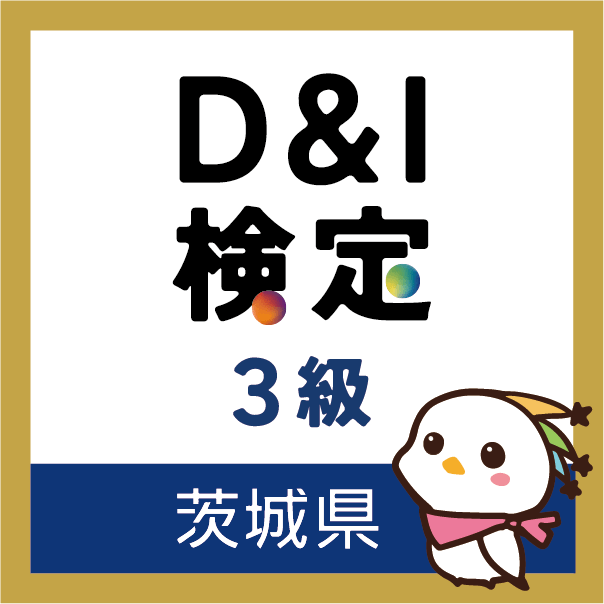 |
||||||||||
| 「お互いさま」を合言葉に ワークライフマネジメントを利用者様の満足度向上へ | ||||||||||||
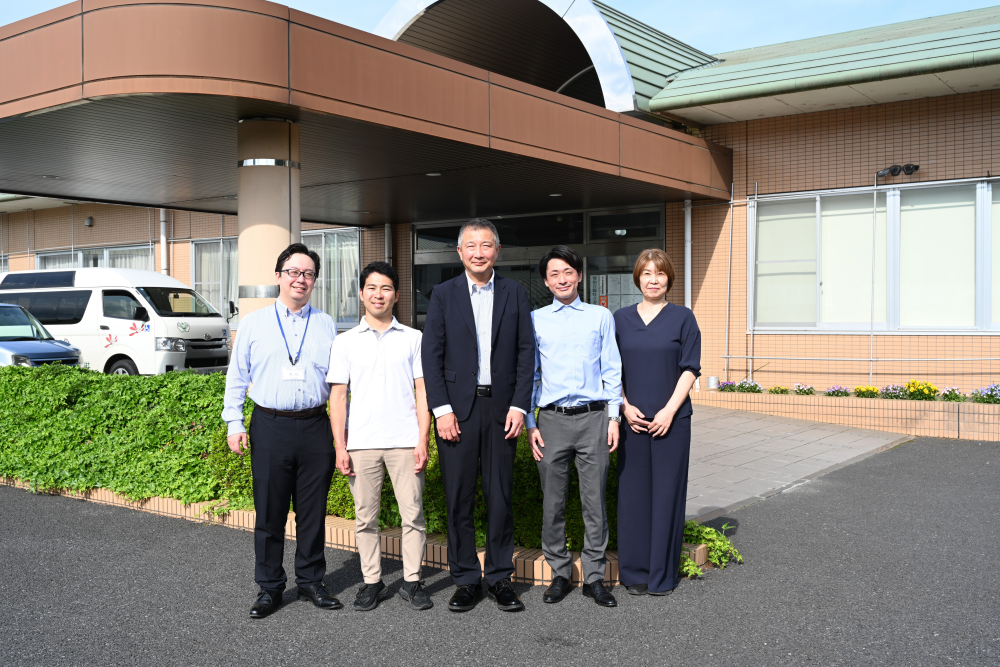 左から 副施設長 谷さん、介護士 石井さん、施設長 高城さん、生活支援課長 國谷さん、事務長 大塚さん
|
||||||||||||
|
||||||||||||