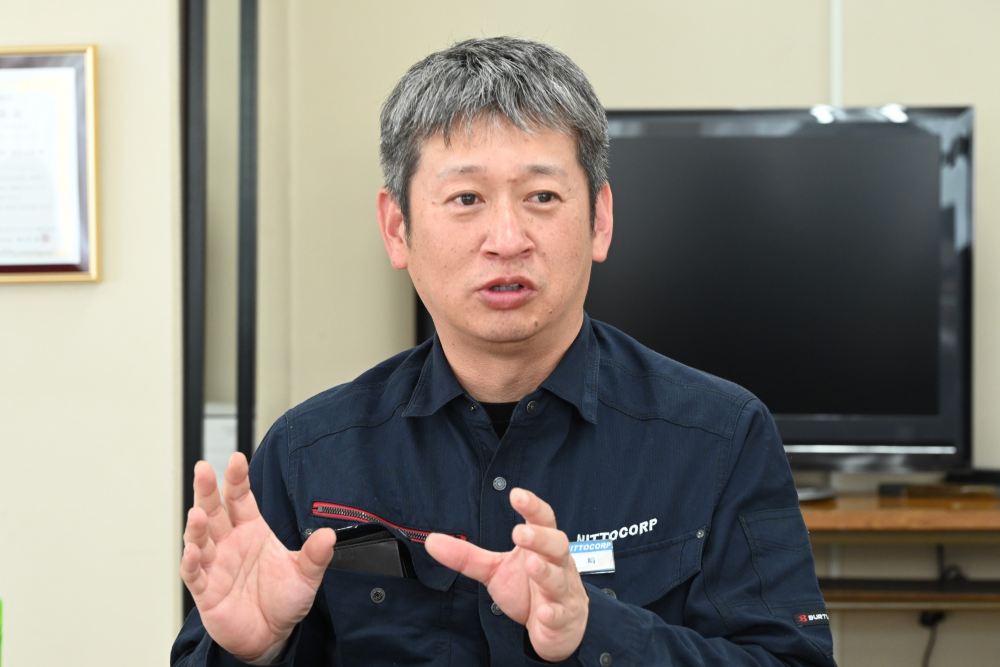ダイバーシティ経営の強みとは⁉ モデル企業のその後の取り組みについて伺いました。
2023年度紹介内容はこちらhttps://www.diversity-ibaraki.jp/dandi/04.html
2023年度紹介内容はこちらhttps://www.diversity-ibaraki.jp/dandi/04.html
 日東電気グループ 日東電気グループ |
D&I推進モデル企業 |    |
||||||||||
| 多様な人材から生まれたイノベーション 技術革新と生産性向上への道 | ||||||||||||
 左から 代表取締役社長 阿部さん、エンジニア タンさん、エンジニア リフキさん、第一製造部 部長 先崎さん
|
||||||||||||
|
||||||||||||